社員ブログ
blog

-

クロマツが来たよ~!!@タカハマカフェ🐫
3月もあと3日! 今週タカハマカフェに行ったりそばを通った人は驚いたのではないでしょうか! タカハマカフェのクロマツを読んだ方は「おっ!」と思われたのではないでしょうか! そう! ついに! クロマツが植樹されました!!よ!!! [caption id="attachment_1910" align="alignleft" width="600"] これはポジションについて植えてもらうのを待っているクロマツ達[/caption] 臨時クエストでテンションがハイになっておりますが、いたって正常(?)なだいちゃんです( ・ω・)ノ はい。 それでは大分県から遠路はるばる鳥取県にやってきたクロマツをご覧ください。 ところで皆さんはこの松が樹齢何年くらいか分かりますか? ヒントは「木の1年の成長=枝から枝」です。 [caption id="attachment_1914" align="alignleft" width="600"] 赤い○から赤い○が1年で成長した長さ[/caption] 会長は写真を見て「9年くらいじゃないか?」と言っていましたが、違っていたんです 根元に枝の跡が7年分あるとは思わないですよね… ということでこのクロマツは樹齢15年でした! (私はそもそも外観で年数が分かることすら知りませんでした😳) この若いクロマツたちは木杭式地下支柱という地上に杭の出ない方法で固定して植樹されました。 5年くらいしたら根が張って、金具を外すことができるそうです。 [caption id="attachment_1916" align="alignleft" width="600"] 木杭式地下支柱を設置してもらったクロマツ[/caption] 植樹が完了して新たな装いになったタカハマカフェへ、是非足を運んでみてくださいね!!! ではまた( ・ω・)ノシ
-

岩美道路が全線開通しました!(⿃取県岩美町)
令和5 年3 ⽉12 ⽇ ⼭陰近畿⾃動⾞道の⼀部を構成する岩美道路が全線開通しました! ⼭陰近畿⾃動⾞道は、⿃取県⿃取市から兵庫県豊岡市を経由し京都府宮津市に⾄る延長120km の地域⾼規格道路です。 ちなみに、その中で岩美道路区間は平成21 年に事業開始し、平成28 年に岩美IC〜浦富IC間が開通し、令和5 年に浦富IC〜東浜IC が開通しました。(総延⻑5.7km) ※引⽤元:⿃取県HP 弊社においても橋梁下部⼯事や道路改良⼯事など、多くの⼯事に携わらせて頂きました。 地域の皆様、関係者の皆様には⼯事に伴い多⼤なる御協⼒を頂きました事をこの場を借りて厚く御礼申し上げます。 弊社が施⼯した岩美道路の写真を少し紹介します。 平成29 年 岩美道路橋梁下部(1⼯区) 令和4 年 国道178号(岩美道路)改良(8⼯区) 他にも多くの⼯事を施⼯しました。 当社HP の「実績紹介」から閲覧することができますので、是⾮ご覧になって下さい。 土木工事|大和建設株式会社 (daiwacc.co.jp) 岩美道路の完成により、沿線では観光客の増加が期待されるほか、救急医療や災害対策のスピードアップが期待されますね! 通勤や移動時間が短縮され、快適になる⽅もいるのではないでしょうか!? 私も近々ドライブがてら通ってみようと思います。 開通直後で混雑しているそうですので、運転の際はお気を付けください。
-

タカハマカフェのクロマツ
2022年8月にオープンした隈研吾氏設計の鳥取砂丘新名所「タカハマカフェ」ですが、実はまだ建物周辺のクロマツの植樹が残っています。 クロマツの植樹時期は2~3月がベストとされ、時期を間違えると根が付かずに枯れてしまうとのことです。 いよいよ植樹するベストシーズンに入ったので、大分県の酒見緑化園さんが管理されている圃場(ほじょう)までクロマツを選びに行ってきました。 当日は、朝4:30に出発し、その日の19:30に鳥取に帰ってくるという弾丸強行スケジュールでした。 圃場には見事なクロマツがたくさんありました。 5時間かけて4か所の圃場を見させていただき、目的のクロマツを決定してきました。 クロマツはトラックで鳥取まで運んでもらい、3月中にはタカハマカフェの外回りに植樹する予定です。 クロマツが植樹されてまた一味違うイメージになるタカハマカフェ、鳥取に来た際にはぜひ立ち寄ってみてください! #常務さんぽ [caption id="attachment_1908" align="alignleft" width="1209"] ※画像はイメージです[/caption]
-

【完成】青谷かみじち史跡公園展示ガイダンス施設新築工事(重要文化財棟・建築)
皆さまのご協力の下、先週、無事に工事完成することができました。 今回この事業に携わることができ、大変感謝しております。 [caption id="attachment_2019" align="alignleft" width="1024"] 2021.12 着工前[/caption] [caption id="attachment_2020" align="alignleft" width="1024"] 2022.5 1階躯体工事[/caption] [caption id="attachment_2021" align="alignleft" width="1024"] 2022.8 仕上着手前[/caption] [caption id="attachment_2022" align="alignleft" width="1024"] 2022.10 足場解体[/caption] [caption id="attachment_2023" align="alignleft" width="1024"] 2023.1 工事完成(公園側より)[/caption] [caption id="attachment_2024" align="alignleft" width="1024"] > 2023.1 工事完成(1階ロビー)[/caption] 展示室の天井前回の「花*花」でも登場した天井です。この天井の花形は青谷上寺地遺跡から出土した「花弁高坏かべんたかつき」という器の浮き彫り部分の花がモチーフになっています。 工事期間中にはオープン前の宣伝イベントにも参加させていただきました。 そこでは関係者の事業に対する熱い思いや、県民の皆さまの関心の高さが肌で感じられ、いつも以上に気持ちの入った現場でした。 オープンに向けて良いバトンタッチが出来たのではないかと感じています。 この施設が多くの方に愛され、親しんでいただけるような場所になればと思っています。 青谷上寺朗さんよろしく!! ★関連記事★ 寒桜 青谷かみじち史跡公園展示ガイダンス施設新築工事(重要文化財棟・建築) 春の便り~いとをかし~ まがたまの日 いよいよ…! 花*花
-

花*花
11月に入り秋も終盤に迫ってきました。 北側の県道から見る重要文化財棟は、サムネの通りただ今見ごろの秋桜がコンクリートの灰色をカラフルに染めてくれています。 さて、青谷かみじち史跡公園展示ガイダンス施設新築工事(重要文化財棟・建築)の現場もあと数か月となり完成まで佳境を迎えています。 花と言えば、展示室の天井にも約6mの大きな花が咲きました! [caption id="attachment_2012" align="alignleft" width="712"] 花弁天井の下地[/caption] [caption id="attachment_2013" align="alignleft" width="722"] 花弁天井[/caption] これからどのような色に染まるのか楽しみです🌸 ちなみに何の花か分かりますか? さぁ考えてみよう!! 【青谷かみじち遺跡 イベント情報】終了しました 『とっとり弥生の王国 青谷かみじちフェスタ』 開催日:2022年11月13日(日) 時間:午前10時~午後3時 場所:鳥取市青谷町農林漁業者トレーニングセンター(青谷中学校となり)他 グルメ、弥生人体験、発掘見学など様々な催しが行われます。 この中には来年オープンする「青谷かみじち史跡公園」の工事の様子を解説付きで見学できるコーナーも予定されています! イベントスタッフと共に工事担当者が解説に参加しますので、ご興味のある方はぜひご参加ください! ▼青谷かみじち史跡公園の工事見学ルート(予定) イベント詳細は「とっとり弥生の王国推進課」で検索してご確認ください。 みなさんのご来場お待ちしています。
-

いよいよ…!
10月も半ばになり秋真っ只中な感じになってきました。 夕暮れの時間も早くなり、気付けば夕方の音楽も18時から17時に…… っと、これは10月1日からでした。 肌寒い日が増えてきましたが、体調には十分に気を付けていきましょう。 さて、今回の内容です。 青谷かみじち史跡公園展示ガイダンス施設新築工事(重要文化財棟・建築)では一部南東側の足場解体が始まり、建物の表情が見えてきました。 月の真下の建物が重要文化財棟です。 打放しコンクリートを基調とした外観になります。 今月中を目途に全ての足場を解体する予定です。 解体後の姿をお楽しみに✨ 前回の記事はこちら 関連記事その1:春の便り~いとをかし~ 関連記事その2:まがたまの日
-

⼯事現場付近を散策すると・・・
10⽉となり、夏も過ぎ去りだいぶ過ごしやすくなってきました。 私が、担当している⼯事は、樗谿(おうちだに)公園の付近の下⽔道をリニューアルする⼯事をしていますが、仕事合間に公園で撮影したものです。 もみじも⾚くなり、秋の訪れを感じさせてくれます。 ⼟⽇、祝⽇になると観光で訪れる⼈や、ランニングする⼈も多く⾒かけます。 こちらは、樗谿公園のマスコットのポニーのハナちゃんです。 天気のいい⽇にいくと会えるかもしれません。 こちらは、現場の前にある喫茶店ですが、⾃家焙煎されたこだわりの珈琲がいただける喫茶店、カプリコーヒービーンズさんです。 ⼯事中に、なんといえないフレーバーな⾹りに誘われ、休憩時間を利⽤しこだわりコーヒーをいただきました。 (ラテアートがきれいなハートの形で飲むのがもったいない) 店内は、リラックスできるようなBGMが流れており濃いめの珈琲(カフェラテ)を味わいながら、優雅な、ひとときを満喫しました。 さて、現在進⾏中の⼯事ですが、場所は以下のとおりです。 ⽼朽化した下⽔道の寿命を延ばすため、道路を掘らずにマンホールから材料を引き込んで既設管の内側に新たに管を形成する⼯事を⾏っています。 ⼯法について詳細は、看板に記載していますので樗谿公園にお⽴ち寄りの際は、是⾮みてみて下さい。 ⻘⾊の部分は、9⽉末に完了しました。 ⾚⾊の部分は、9⽉26⽇〜11⽉中旬頃まで施⼯する予定です。 現道沿いでの交通規制しながらの⼯事となるため、事故を起こさないよう安全・安⼼に施⼯していきます。 ⼯法説明看板(⼤⼝径) ⼯法説明看板(⼩⼝径)
-

米原家住宅上門及び塀改修工事
米原家住宅を聞いたことはありますか? 米原家住宅は鳥取市名誉市民の米原章三氏の邸宅でもあり、智頭宿の国指定重要文化財 石谷家住宅の近くにあります。 [caption id="attachment_2245" align="aligncenter" width="1024"] 修繕前の全景写真[/caption] そんな米原家住宅は主屋・土蔵・上門及び塀・下門及び塀が「国登録有形文化財」また、国選定重要文化財的景観「智頭の林業景観」の構成要素になっています。 しかし近年、塀の腰板や土台、柱などの経年劣化が進み、捲れ・割れ・腐食・倒れなどを起こしていました。 [caption id="attachment_2244" align="aligncenter" width="800"] 修繕前その1[/caption] [caption id="attachment_2243" align="aligncenter" width="800"] 修繕前その2[/caption] [caption id="attachment_2242" align="aligncenter" width="800"] 修繕前その3[/caption] そこで、新規材料として柱に内地栂、控柱と土台に内地栗を使用し土台の取替え、柱・控柱は根継ぎを行って修繕をしました。 (内地=国産材の意味です) 土台の継手には「二方車知栓繋ぎ(にほうしゃちせんつなぎ)」、柱・控柱の根継ぎには「金輪繋ぎ(かなわつなぎ)」を基本とします。 [caption id="attachment_2248" align="aligncenter" width="800"] 土台の継手:二方車知栓繋ぎ[/caption] [caption id="attachment_2235" align="aligncenter" width="800"] 柱の継手:金輪繋ぎ[/caption] また、控柱の足元には新たに基礎石を設けました。 工期中には近くの県立智頭農林高等学校の生徒を招き、文化財保存の意義・工法等の講義が行われました。 [caption id="attachment_2238" align="aligncenter" width="800"] 真剣な様子で講義を受けている生徒たち[/caption] [caption id="attachment_2237" align="aligncenter" width="800"] 仕口・継手の模型を通じて実際の工法に触れてもらった[/caption] 文化財の改修工事は元々使用されている材をできる限り残しながら、柱梁仕口や接合部など本来あるべき状態で加工し、伝統的意匠を崩さないことが重要なポイントになってきます。 今回の米原家住宅をはじめとして私たちの周りには残していきたい風景や建築物がたくさんあり、改修工事を通じてこれからも貢献できたらと考えています。 今回の記事は文化財修繕工事のため、継手などの専門用語がいつもより多めにでてきましたが、大和建設は文化財の改修工事の仕事も行っていることを知っていただけたら幸いです。
-
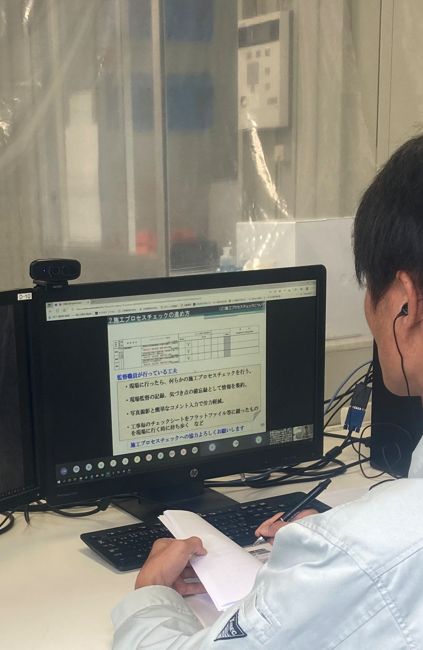
建設業のリモートワーク
今回は建設業のリモートワークを紹介します。 新型コロナウイルスの影響や建設業のICT 化により、 建設業界でもいわゆる「リモートワーク」が⾏われています。 安全大会 ウェブ講習、会議 写真のように会社⾏事や会議・講習などをリモートで⾏っています。 この他、⼯事現場での検査や⽴会もリモート化が進んでおり、 「遠隔臨場」と名付けられています。 建設業は⽇進⽉歩! 波(ウェーブ)に乗っていきましょう!(ウェブだけに)
-

タカハマカフェ完成式典
令和4年8月5日(金)、鳥取市の砂丘会館に完成した「タカハマカフェ」の完成式典が開催されました。 神事、テープカット、竣工式の様子を紹介します! ~神事~ 当初よりも出席者が増えましたが、2階のフロアを使用することで完成した建物の中で実施することができました。 ~テープカット~ 1階入口前の広場で実施することにしていましたが、神事の最中やテープカット予定時刻の少し前に雨が降って心配しました。 しかし、司会者の方が過去全てのテープカットを晴れにしてきた歴戦の晴れ女ということもありテープカット前には太陽が出てきて、よいコンディションで行うことができました。 ~竣工式~ 会議が入り欠席となった平井知事がリモートで所定の時間に入りたいとのことで、司会者と調整し、式次第内容をタイムスケジュールに合わせ前後させ、無事知事リモート挨拶も尺の中に入り大成功の竣工式となりました。 今回の物件は有名建築家 隈研吾さんが設計されたので、完成式典に出席していただくべく2ヶ月前から日程を詰め準備をしてきました。 ところが、様々な事情から工事途中に竣工式を迎えてしまうのではないかと心配な時期もありましたが、関係者の皆さまの努力で無事この日を迎えることが出来ました。 ありがとうございました。 このタカハマカフェは明日、令和4年8月20日グランドオープンですのでぜひ行ってみてくださいね!!
お問い合わせ
contact
