社員ブログ
blog

-

研修会のはなし
5/30(火)、大和建設で交通安全講習会と人権問題研修会が開催されました。 交通安全講習会の講師に日本海自動車学校からお越しいただき、「あおり運転」「ながら運転」の危険性を主に勉強させていただきました。 続いて休憩をはさんで人権問題研修会が鳥取市人権教育推進員の方をお招きしてスタートしました。 内容は「人権問題と企業責任」「グローバル化による多様化の時代を迎える企業と人権問題」というもので、企業の社会的責任についてであったり国際的な人権の流れ、日本と海外のCSRの違いなどのお話を聞きました。 学んだ交通安全意識と人権意識を基に気を引き締めて過ごしていきたいと思います。
-

JUIDA認定スクール(ドローン講習)
先日、株式会社skyerさんのドローン講習を受けてきました。 場所は鳥取砂丘の近くにある「SANDBOX TOTTORI」さん! 講習は3日間で1日目、2日目は座学・実技の授業、3日目は座学・実技それぞれの試験がありました。座学ではドローンを飛ばす上で大切な知識や法律などを勉強し、実技では基本的な操縦技能を学びました。 ドローンを飛ばすのは私が想像してよりも難しかったです。特にGPSが切れた状態だと風の影響で機体が明後日の方向に行くので、コントロールするのに慣れが必要です。 実技試験の時は緊張で手が震えてました。無事3日間の操縦技能、安全運行管理者の講習を終えました。 ドローンは現在では空撮、測量、農薬散布など多種多様に活用されています。災害発生時に人が立ち入ることが困難な場所でも迅速にアプローチでき、被害状況の把握もできます。今後ドローンがどんどん有効活用されていくと思うので、ドローンについてこれからもっと勉強していきたいと思います。 SANDBOX TOTTORIさんはカフェも併設しており、3日間そこで昼食をとりました。 注文した料理はどれも美味しく、個人的に一番美味しかったのはガパオライスサラダボウルです!気になった方はぜひ食べにいってみてください!
-

GW休暇
みなさんは今年のGW をどのように過ごしましたか? 私のGW(ゴールデンウィーク)は有給を2 日取得し、9 日間の超大型連休でした。 ここ2、3 年はコロナ禍で旅行に行くことが難しかったですが、 規制も緩和されたということで、今回は京都に行ってきました! 今回の旅の一番の思い出は、清水寺へ参拝に行ったことです。 コロナ規制緩和後のGW 休暇ということで、観光客でいっぱいでした。 その後は、京都の名物料理「にしんそば」を頂きました! お店は“松葉”というお店です! 有名店らしく観光客でにぎわっていました! やはり京都はグルメ、神社やお寺など観光スポットがたくさんありオススメです。 皆さんも行ってみてはいかがでしょうか。
-

#大和建設施工紹介@福田家住宅
どうも、だいちゃんです(。゚ω゚)ノ GWが終わってやっと1週目が終わりに近づきましたね! みなさまいかがお過ごしでしょうか? だいちゃん的GWの1番の思い出はお祭りを1日ずっと追い続けたことです💪 なかなか迫力があってたのしい1日になりました😊 それでは今回の内容に入っていきましょう! 10年前、平成25年に母屋の茅葺屋根のふき替えを行った大和建設ですが、今回は「上の蔵」の修繕工事を行っています! Twitterをチェックしている方は見覚えのある写真が多くなっていますが、最後までお付き合いよろしくお願いします😊 まずは福田家住宅を簡単に説明するとですね… 「江戸時代初期(約400年前)以前に建てられたと推測される県内最古の住宅建築で、国指定重要文化財」です。 その「上の蔵」(写真左隅にちらっと見えてる建物)の解体修繕工事ということで、解体しても基本的に同じものをそのまま元の場所に戻すルールを守り、瓦には1枚ずつ番号を振って丁寧に下ろして作業で出てきた土も再利用できるように集めて、漆喰で出来た「鏝絵(こてえ)」もきれいに外していきます。 さて、この建物ですが、蔵なので耐火性が高い作りになっています。 特に特徴的なのが、二重屋根という構造です。 瓦屋根の下に土居塗という土の屋根があるので、蔵の中が燃えない・燃えにくい造りになっています。 [caption id="attachment_3136" align="aligncenter" width="600"] 二重屋根の構造はこんな感じ。[/caption] そしてそれぞれの矢印から見た写真が以下の4枚となっています。 [caption id="attachment_3132" align="aligncenter" width="768"] ① 蔵の中から撮影[/caption] [caption id="attachment_3133" align="aligncenter" width="768"] ② 瓦を外したところ[/caption] [caption id="attachment_3134" align="aligncenter" width="768"] ③[/caption] [caption id="attachment_3135" align="aligncenter" width="768"] ④ 1番奥に見える木材が「軒桁(のきげた)」[/caption] 写真を見てわかるように木材の下に見える土の部分が土居塗の部分となっています。 始めてみるものが多くて調べながら書いているのでふわっとした内容になりましたが、今後も読んでいただけると嬉しいです。 それでは今回はこの辺で( ・ω・)ノシ
-
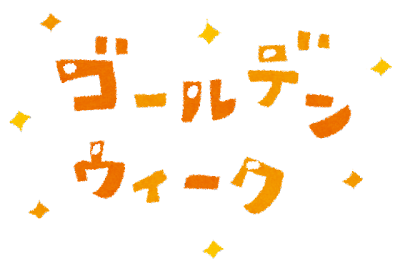
やってみよう!でー(day)
とある日の出来事です。 私には中学生の息子がいますが、その息子から「5/1、5/2休みだけぇ」と言われ、あれ、平日のはずなのにと思い保護者便りを見返すと、「やってみよう!でー(day)」のお知らせが書いてありました。 「やってみよう!でー(day)」とは市立の幼稚園、小・中学校で、4月末からゴールデンウィークと文化の日の前後の平日が体験的学習活動等休業日としてお休みになります。 コロナ禍で大きく制限を受けた子どもたちの活動機会をつくり、家庭や地域でのふれあいがより一層深まることを目的とした休業日で、鳥取市ではネット投票の結果「やってみよう!でー(day)」と名称が決まったそうです。 息子はなんと9連休・・・ せっかくなので私も明日は有給をとって、息子と一緒にどこかに出かけたいと思います。
-
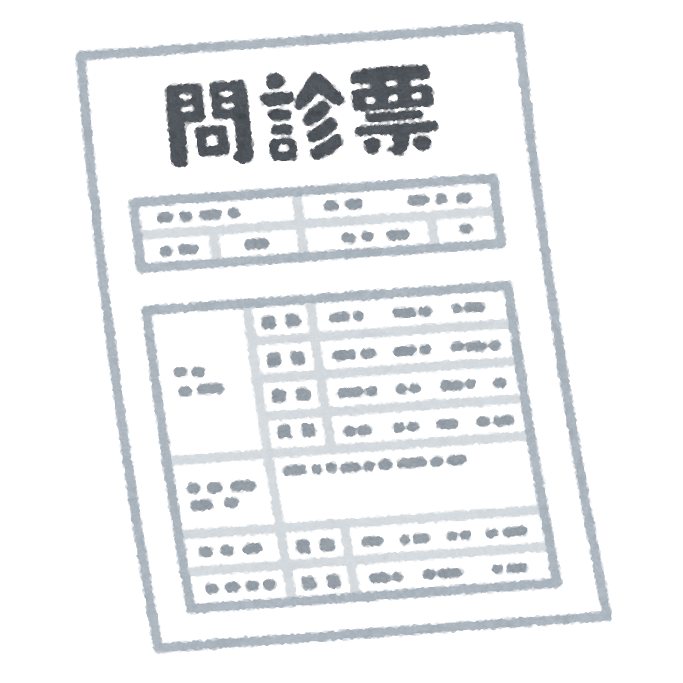
健康診断
新年度に差し掛かりました。 新年度から環境が変わった方も多いと思いますが、少しずつ慣れてきた頃でしょうか。 さて、先日事業所定期健康診断に行ってきました! 毎年の事ですが、採血は何回しても苦手です。 普段生活していると健康のことについてそれほど意識せずに生活している部分も多いですが、改めて日頃からの定期的なメンテナンスや体調管理など意識することも大事なことだと感じました。 みなさんも健康診断をしっかり受けて、今の自分の健康状態をきちんと把握しましょう。
-

とあるゴルフコンペにて
3月某日、某所、曇り空の下、ゴルフコンペに参加してきました。 当日イベントとして、午前午後、各組がスタート前にドラコンプロの豊田竜宏プロと長谷川円香プロにティーショットのデモンストレーションを見せていただきました。 午後のスタート前に長谷川円香プロのティーショットを見ましたが、流石プロ、どこまでも飛んでいく球を感心しながら眺めていました。 そのあと、スタートしましたが、差は歴然。感服いたしました。 これからの豊田竜宏プロと長谷川円香プロのますますのご活躍を期待しています。
-

令和5年度 新⼊社員研修
4⽉3⽇、弊社では⼟⽊部2名・建築部1名の新⼊社員を迎え、本社にて⼊社式を⾏いました。 ⼊社式後、さっそく新⼊社員研修も⾏われました。 おおまかな仕事の流れなどの説明や⽣コンクリートなどの⼯場⾒学等 2⽇間研修がありましたが真剣な⾯持ちで取り組んでいました。 新⼊社員研修会状況 コンクリート⼯場⾒学状況 最初は仕事を覚えるのが、いろいろ苦労すると思いますが、 あきらめずに仕事を覚えていって欲しいと思います︕︕
-

クロマツが来たよ~!!@タカハマカフェ🐫
3月もあと3日! 今週タカハマカフェに行ったりそばを通った人は驚いたのではないでしょうか! タカハマカフェのクロマツを読んだ方は「おっ!」と思われたのではないでしょうか! そう! ついに! クロマツが植樹されました!!よ!!! [caption id="attachment_1910" align="alignleft" width="600"] これはポジションについて植えてもらうのを待っているクロマツ達[/caption] 臨時クエストでテンションがハイになっておりますが、いたって正常(?)なだいちゃんです( ・ω・)ノ はい。 それでは大分県から遠路はるばる鳥取県にやってきたクロマツをご覧ください。 ところで皆さんはこの松が樹齢何年くらいか分かりますか? ヒントは「木の1年の成長=枝から枝」です。 [caption id="attachment_1914" align="alignleft" width="600"] 赤い○から赤い○が1年で成長した長さ[/caption] 会長は写真を見て「9年くらいじゃないか?」と言っていましたが、違っていたんです 根元に枝の跡が7年分あるとは思わないですよね… ということでこのクロマツは樹齢15年でした! (私はそもそも外観で年数が分かることすら知りませんでした😳) この若いクロマツたちは木杭式地下支柱という地上に杭の出ない方法で固定して植樹されました。 5年くらいしたら根が張って、金具を外すことができるそうです。 [caption id="attachment_1916" align="alignleft" width="600"] 木杭式地下支柱を設置してもらったクロマツ[/caption] 植樹が完了して新たな装いになったタカハマカフェへ、是非足を運んでみてくださいね!!! ではまた( ・ω・)ノシ
-

蒲公英を踏みて測量始まりぬ
まずはこれだけ言わせてください。 WBC侍ジャパン優勝おめでとうございます!!!!!!!!!!!!! いやぁ、決勝戦の情報を見るだけでも緊張しちゃってました(;・∀・) 家に帰ってからゆっくり見たいと思います。 どうも、心臓バックバク手汗MAXだいちゃんです。(。゚ω゚)ノ タイトルの通り内容は野球全く関係ないんですが、気を取り直して 3月21日の春分の日をすぎ、暦の上でも春となりました。 まだ冷える日もあるみたいですが、皆さまいかがお過ごしでしょうか。 このタイトルの俳句は親戚が趣味で詠んだ俳句です。 「たんぽぽ=春」「測量=新しいこと」って感じがして今の時期っぽいなと思ったんですけど、よくよく考えてみると「測量が始まっちゃって、たんぽぽが踏まれてしまった」なのかな?とも思いました。 まぁ、今となってはどんな気持ちで詠んだのかは分からないのですけどね! さて、今年は全国的に桜前線の到来が早いらしく、先週東京では桜の開花宣言がありましたね。 鳥取の予報では3/21に開花宣言かな?となっていましたが、一昨年に引き続き最速の3/19に開花宣言となりました。 満開の桜のライトアップが今から楽しみですね!! ということで、前回のブログ担当後から今日までにストックされた建築部の春写真をかいつまんでご紹介します🌸 今現在で2023年3月分の写真は25枚ストックされているんですよね…紹介しきれなかった分はTwitterでも使っていきます。 [caption id="attachment_1925" align="alignleft" width="800"]立川の梅 (撮影日:2/21)[/caption] [caption id="attachment_1926" align="alignleft" width="800"]マンサクの花 (撮影日:3/1)[/caption] [caption id="attachment_1927" align="alignleft" width="800"]春はもう少し (撮影日:3/3)[/caption] [caption id="attachment_1928" align="alignleft" width="800"]梅花 春はすぐそこへ (撮影日:3/4)[/caption] [caption id="attachment_1929" align="alignleft" width="800"]今日の大山@常務さんぽ (撮影日:3/4)[/caption] [caption id="attachment_1930" align="alignleft" width="800"]福田家住宅の梅 (撮影日:3/7)[/caption] [caption id="attachment_1931" align="alignleft" width="800"]椿 (撮影日:3/9)[/caption] [caption id="attachment_1932" align="alignleft" width="800"]庭にふきのとう (撮影日:3/10)[/caption] [caption id="attachment_1933" align="alignleft" width="800"]原木シイタケ (撮影日:3/10)[/caption] [caption id="attachment_1934" align="alignleft" width="800"]菜の花 (撮影日:3/10)[/caption] [caption id="attachment_1935" align="alignleft" width="800"]つばき (撮影日:3/11)[/caption] [caption id="attachment_1919" align="alignleft" width="800"]沈丁花 (撮影日:3/11)[/caption] [caption id="attachment_1920" align="alignleft" width="800"]黄水仙 (撮影日:3/11)[/caption] [caption id="attachment_1921" align="alignleft" width="800"]山茱萸(サンシュユ)(春黄金花(ハルコガネバナ)) (撮影日:3/16)[/caption] [caption id="attachment_1922" align="alignleft" width="800"]ツルニチニチソウ (撮影日:3/16)[/caption] [caption id="attachment_1923" align="alignleft" width="800"]さくら (撮影日:3/16)[/caption] タイトルにたんぽぽって入れてたので探したりしていたんですけど、不思議とたんぽぽって見かけなくなった気がするんですよね おとなになったからなのか環境の変化なのか分からないですけど ということで、春の空気が少しでも伝われば嬉しいです。 それでは(・ω・)ノシ
お問い合わせ
contact
